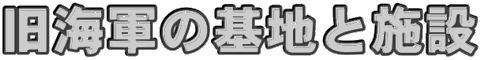| 青 森 |
: |
昭和8年に青森県東津軽郡油川村(現青森市油川町)の羽白に民間の 油川飛行場 として開設され、同12年には大日本航空 (株) の東京 ~ 札幌線の中継地となりましたが、これは昭和15年には廃止されたようです。 昭和16年に旧陸軍の基地に転用されて同18年頃から拡張工事が行われましたが、大戦中の運用状況などは不詳です。 終戦後は米軍に接収されたものの、昭和22年には接収解除となり、用地はその後引揚者の入植地となったようです。 現在では用地の大部分は住宅地となっていますが、衛星写真で見る限りでは土地の区画割りに終戦時の状況が残されています。 |
| 淋 代 |
: |
青森県三沢村に置かれた飛行場ですが、何故か旧陸軍側の史料には全く出てきませんで、大戦中の米軍史料によって地図及び写真と共にその概要が知られている航空基地です。 大戦中の状況についても全く不明ですが、戦後はそのまま放棄又は民間に払い下げられたようで、現在の衛星写真を見る限りでは基地跡を示すものは何もないようです。 なお、本飛行場と戦前
「ミス・ビードル号」 の太平洋無着陸横断飛行の離陸地で知られる現在の淋代海岸にあった臨時滑走路とは全くの別物です。 |
| 八 戸 |
: |
昭和15年に青森県八戸市高舘の八太郎沼の用地を買収し同16年に整備されたものですが、大戦中の運用状況については不詳です。 終戦後は米軍の Camp Haungen として使用され、この間に南側に新たな滑走路が建設されました。 米軍は昭和31年に撤退、替わって元の飛行場地区は陸上自衛隊八戸駐屯地、新滑走路地区は海上自衛隊八戸基地となり、こちらは一時航空自衛隊及び民間機も使用しました。 現在では元の飛行場地区は滑走路及び誘導路の一部が残っていますが、航空機の運用はなされていません。 |
| 能 代 |
: |
秋田県能代市東雲村の東雲原に置かれた飛行場で、所在地名から通称 東雲飛行場 とも呼ばれました。 昭和12年の適地調査により設置が決定され、同15年に開設されたものです。 (一部には昭和12年に用地が旧陸軍に献納されたとの説もありますが根拠不明です。) 大戦中の運用状況などは不詳ですが、終戦後は民間に払い下げられて開拓地となり、現在でも農耕地が広がる田園風景が広がっています。 |
| 岩 手 |
: |
昭和13年に地元有志団隊から旧陸軍に献納されたもので、所在地名から通称 後藤野飛行場 とも呼ばれました。 訓練基地として使用された後、昭和19年頃以降は実用基地となりました。 終戦後は米軍の手により飛行場施設は破棄され、用地は民間に払い下げられて開拓団が入植して田園地帯となった他、現在では一部は工業団地となっています。 |
| 真室川 |
: |
昭和15年に山形県最上郡豊里村 (現真室川町) の藍野原に旧陸軍の訓練基地として整備されたものですが、元々は昭和11年に村立の飛行場として開設されたともされています。 熊谷陸軍飛行学校の分教場が置かれていたとされていますが、大戦中の運用状況なども含め詳細は判りません。 戦後は民間に払い下げられ、現在でもほとんどが農耕地となっています。 |
| 宮城野 |
: |
宮城県仙台市の市街にある旧陸軍の宮城野原練兵場を飛行場としても使用したもので、昭和8年に南南東約3kmの霞目に飛行場が出来て以降は 仙台第一飛行場 とも呼ばれていました。 なお、この昭和8年以降は旧陸軍の飛行場としては使用されなかったとするものもありますが、米軍史料では大戦中も運用されていたとされています。 終戦後は米軍の2つの駐屯地に挿まれた形になったため特に活用はされなかったようで、米軍撤退後の昭和24年には総合運動公園としての整備が始まり、現在では跡地の西側約半分が競技場や球場を備えた宮城野原運動公園となり、東側はJRの貨物コンテナ・ヤードとなっています。 |
| 仙 台 |
: |
昭和8年に宮城野飛行場の南南東約3kmの霞目 (現仙台市若葉区霞目) に整備されたもので、所在地名から通称 霞目飛行場、又は 仙台第二飛行場 とも呼ばれました。 大戦中の運用状況などについては不詳です。 終戦後は米軍の駐屯地となりましたが、昭和32年に撤退後は陸上自衛隊の霞目駐屯地となり、東方方面航空隊(現東北方面輸送隊)が置かれました。 |
| 増 田 |
: |
昭和15年に宮城県名取郡下増田村 (現名取市下増田) に開設された飛行場で、熊谷陸軍飛行学校の分教場が置かれた訓練基地ですが、大戦中の運用状況などについては不詳です。 終戦後は米軍に接収されましたが、昭和31年に解除・返還され、翌32年に防衛庁と運輸省の共同使用の仙台飛行場となりました。 昭和39年には仙台空港と改称、昭和47年には新たにB滑走路が増設され、以後このB滑走路の延長を中心にして拡張・近代化が行われてきました。 平成3年には国際空港となりましたが、平成23年の東日本大震災で大きな被害を受けたことはご承知のとおりです。 平成28年には完全民営化されて、現在に至っています。 |
| 原 町 |
: |
昭和15年に福島県相馬郡原町 (現南相馬市) の雲雀ヶ原に設置されたもので、所在地名から通称 雲雀ヶ原飛行場 とも呼ばれています。 開設当初は熊谷陸軍飛行学校の分教場が置かれ、翌16年~17に明野陸軍飛行学校、水戸陸軍飛行学校、次いで鉾田陸軍飛行学校と点々とその所管が替わったものの、旧陸軍の訓練基地として使用されました。 昭和19年からは特攻隊の編成・出撃基地となったとされています。 終戦後は民間に払い下げられて主として農耕地となりましたが、現在では次第に南相馬市の住宅街が広がってきているようです。 |
| 磐 城 |
: |
昭和17年に福島県双葉郡熊野村 (現双葉郡熊野町) 夫沢の長者ヶ原に設置されたもので、所在地名から通称 夫沢飛行場 あるいは 長者ヶ原飛行場 とも呼ばれています。 開設当初は宇都宮陸軍飛行学校の分校が置かれて訓練基地として運用され、昭和20年には特攻隊の編成・出撃基地となったとされています。 戦後は用地の約半分が製塩関係の用地となり、残りは元の地主に払い下げられましたが、一帯は昭和37年に東京電力の所有地となり、昭和41年に原子力発電所の建設が着工されました。 そうです、ここはまさに先の東日本大震災で原発事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所となっているところです。 |
| 矢 吹 |
: |
昭和12年に福島県西白川郡矢吹町の矢吹が原に設置されたもので、所在地名から通称 矢吹が原飛行場 とも呼ばれています。 昭和15年に熊谷陸軍飛行学校の分教場が置かれ、以降本格的な訓練基地として運用されました。 終戦後は開拓者の入植地となり、一帯は農耕地が広がる田園地帯となりましたが、現在では宅地かも進んできているようです。 |